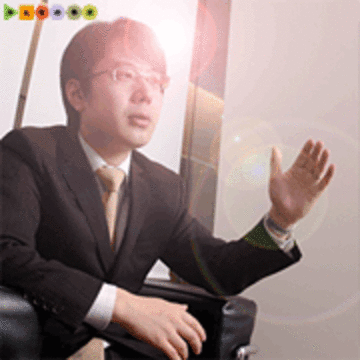────────────────────────────────────
●【本日のニュース】/ストレステストは本物か
────────────────────────────────────
「投資家と一般市民にかなりの安心感を与えるはずだ」--。米連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長は大手金融機関の資産査定(ストレステスト)の結果発表を踏まえた7日の記者会見でこう強調した。
ストレステストでは対象となった19社のうち10社で合計746億ドルの資本不足が指摘されたものの、裏返せば米金融システムの問題が目に見える形で透明化されたことになる。実際、ストレステストの結果を受けたニューヨーク株式市場の時間外取引で米銀大手シティグループやバンク・オブ・アメリカの株価は上昇した。投資家の不安感が和らいだためだ。
もっとも、日本の経験を振り返れば、金融機関の財務が原因となった景気悪化はそう簡単に終息するのもではないはず。「ストレステスト」は本物なのだろうか。(中略)
今回の金融危機をいち早く予言し、「破滅博士」との異名を取るニューヨーク大学のルービニ教授。同教授が率いる米調査会社RGEモニターがストレステストの発表直後に公表したリポートは、「国際通貨基金(IMF)の試算によると、米銀は近い将来合計1兆ドル強の評価損を計上し、資本不足額は2750億ドルにのぼる」、「RGEの試算では6500億ドルの資本不足」などと記載し、ストレステストの「甘さ」への批判をにじませた。
極秘のはずのストレステスト関連の情報が事前に何度も流れ、それが株価を押し上げるなどしてきたこれまでの経緯も疑心暗鬼につながっている。
ノーベル経済学賞を受賞したプリンストン大学のクルーグマン教授は自身のブログで「すべては外部の反応を見るための観測気球だったという見方がある。ストレステストは市民が喜んで受け入れるような内容に変えられたようにもみえる」などと語っている。
(2009/05/11日経速報ニュースより抜粋)
────────────────────────────────────
【ニュースの深層】ストレステストに対する“発想の誤解”が蔓延している
────────────────────────────────────
■いつもメールマガジンをお読みいただきありがとうございます。
経済アナリスト、木下晃伸です。
■悲観論一色だった株式市場に明るさが戻り始めています。しかし、いわゆるプロと呼ばれる人の中で「悲観論で有名な人」は、いまこのタイミングは難しい立場に立たされていると言えるでしょう。
私は、3月中旬に投資姿勢を完全に強気に転換し、当メールマガジンで作成をすると宣言した【緊急特別リポート】では、「株価暴騰の予感」とお伝えさせていただいたわけです。
実際、株価が大きく上昇すると、投資家の見方は一変するのは世の常。悲観論者は、株価上昇を見逃した「曲がり屋」と言われてしまう可能性もあります。
だからといって、簡単に自説を覆すことは難しい。
■というのは、実際の投資の世界に身を置いていない悲観論者からすれば、直近の株価上昇は、どうにも理解の範疇を超えているからです。
彼らの理論通り、現在の株価上昇が実際に一過性で、再び下落するようなことがあれば悲観論者の意見は凄い、ということになります。
一体、どちらと考えるべきなのでしょうか。
■それを考える上で、いま、悲観論の中から聞こえてくる「ストレステストは甘すぎるのではないか」という意見に耳を傾けることは有意義なことだと考えています。
というのも、そもそもストレステストは、「甘く作られている」に決まっているという発想がなされていない意見が多いからです。
■そもそも、10兆円を超える大手銀行をさらに19行も、たった2ヶ月で資産査定を行うということ自体最初から「無理」ではないか、というのが、銀行員経験者としての私の実感があります。
また、日本で言えば、今回のストレステストは、2002年10月に発表された「金融再生プログラム」と同じです。資産査定を厳格化し、不良債権の所在をハッキリさせたことで、意義のある施策でした。
実際、その後、金融機関の多くは、業績を大幅に下方修正させ、期初には、黒字予想をしていた大手メガバンク各行は、最終的には大幅な赤字に転落、合計赤字額は約5兆円にも上ってしまったのです。
つまり、本来的には、「資産査定を厳格化した後に業績が悪化する」ものです。
■しかし、今回のストレステストは、テストを行うのとほぼ同時期に、シティを実質的に国有化する、という決断を下しています。
こんなおかしなことはありません。というのも、ストレステストを行う前に、シティを国有化するということは、シティはストレステストに合格できないということを、当局は知っている、ということになるからです。
でも、当然知っていたに決まっています。それぐらい、金融機関というのは、当局の管理下に置かれているものですから。
■つまり、シティ国有化と同時に、ストレステストが発表されたということ自体、もう金融機関に対しては「甘い」ということは最初から分かっていることなのです。
実際、ストレステスト後に業績を大きく悪化させた金融機関は皆無です。
ただし、甘いということは、株価を“下落”させる可能性もある。だから、元々私は、ストレステストの結果がハッキリする「4月末」までは株価下落の可能性がある、とストレステストが実施されると分かった2月末には考えていました。
■それを3月10日のシティグループ、パンディットCEOの発言「シティが1-2月黒字に転換した」という小さな記事を見て、強気姿勢に転換した理由は、「ストレステストの途中に出たニュース」だったから。
ストレステストは、本来戒厳令がしかれてもおかしくはありません。特に、世界中から注目が集まっているトップの発言は、自由にできるわけがない。
ということは、シティのトップ発言には、米国当局の、金融機関の株価を、ひいては、世界の株式市場を上昇させようとする「出来レース」と見なければならない、と考えた訳です。
■日本でもそうでした。
かつて竹中平蔵経済財政・金融担当相(当時)は、自身が中心となって金融再生プログラムを実施後、2003年3月に「上場投資信託(ETF)は絶対にもうかる」と発言しています。
これは、政治家のリップサービスとしてずいぶんやり玉に挙げられましたが、私は、「株価が上がる自信がある」と考えたのです。実際、その後、日経平均株価は、大幅な株価上昇を果たし、その後、竹中バッシングはパッタリ止んだように思います。
いずれにせよ、そもそも当局が出してくる動きというのは、「恣意性」がある可能性を排除してはいけない。
その背後に隠れている事柄を、自分なりの仮説を持って分析していくと、今回のストレステストは、本物かどうか、ということではなく、「株価を上げるための施策である」とシンプルに考えるべきではないか、と私は考えています。
(文責:木下晃伸 きのしたてるのぶ)
------------------------------------------
■■とうとう、株式市場に【新展開】が訪れ始めた■■
木下 晃伸がお伝えするゴールドレポートのお申し込みはコチラ!
http://terunobu-kinoshita.com/mailmagazine.html
【アマゾン総合1位】木下 晃伸氏 ★新刊
デジタルネイティブの時代―2000万人があなたの味方になる、新ネット戦略とは?
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4492556419?ie=UTF8&tag=masstune01-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4492556419
------------------------------------------
- 運営会社
- 利用規約
- プライバシーポリシー
- 特定商取引表示
- ご利用上の注意(関連法規)
- 広告掲載・取扱商品
- ヘルプ/お問い合わせ
- サイトマップ
- ご注意【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、東京商品取引所、堂島取引所、 S&P Global、S&P Dow Jones Indices、Hang Seng Indexes、bitFlyer 、NTTデータエービック、ICE Data Services等から情報の提供を受けています。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 『みんかぶ』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者、情報提供者及び企業IR広告主は一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「証券取引等監視委員会への情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。 また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
2009/05/11 - 木下 晃伸さんの株式ブログ。タイトル:「ストレステストに対する“発想の誤解”が蔓延している」 本文:──────────────────────────────────── ●【本日のニュース】/ストレステストは本物か ────────────────────────────────────

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます
※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
\ 30日間無料で体験しよう /
みんかぶプレミアム会員になる すでに会員の方はログイン