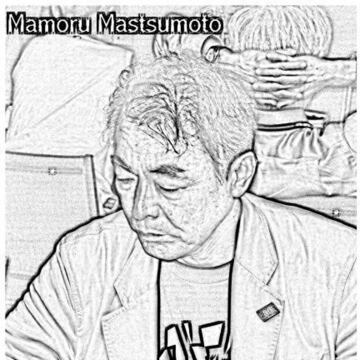前から碁のことを棊(キ)と書いてあるのを知っていたが、その違いが翔年は分っていなかった。前エントリーの渡部義道著「古代囲碁の世界」にこの違いが分りやすく書いてあるのを見つけたので、要約して記しておきたい。
1 碁は棊、棋と同じで、いずれも「キ」と発音する。
2 わが国では囲碁(棊)・将棋と言うように碁と棋が区別して使われてきた。
3 囲碁を囲棊と書いている例は懐風藻(日本最古の漢詩集)にあるぐらいで、ほとんどは囲碁が使われている。
4 倭名類聚抄(倭名抄)に「囲碁。音は棋(キ)、字は棊もある。世間で言う五(ゴ)」と註があるという。これから一般にゴと読んでいたことが窺える。
5 中国では棊・棋と書くのが通例。発音はキ。
6 何故わが国で碁・棊をキと読まずにゴと読んだのか? 大言海によれば碁(ゴ)は棊(キ)の呉音だという。そういうことなら、日本での発音は、揚子江下流・呉地方の発音を取り入れたと考えられる。
7 もしそうだとすると、囲碁が日本に伝来したルートや次期などにかかわりがあるように思える。
8 そういえば囲碁が日本に伝来したころ棊子(ゴイシ)が木から石に変っていたのだ。それで囲棊から、囲碁になったと考えるのはそれほど不自然とは思わない。
※倭名類聚抄(倭名抄)=ワミョウルイジュウショウ。源順(ミナモトノシタゴウ)が後醍醐天皇の皇女のために編述したといわれる最初のいわば漢和百科事典。
これだけお世話になった「古代囲碁の世界」である。著者渡部義道とはどんな人であったのか、あとがきにも興味の尽きない人名が多くでてくるのでそれも合わせて記してお礼の気持ちに代えたい。
渡部義道:戦後、民主主義科学者協会幹事長、日本学術会議会員、衆議院議員。永らく文人囲碁界の世話役を野上彰氏と務めておられた。(世話役の途中、昭和15年11月、治安維持法関係で二度目の牢屋生活を送られています)
ところで、その文人囲碁界の名簿を拝見したら誰でも驚きます。時の文人墨客が綺羅星のごとく並んでいます。
文壇では村松梢風・豊島与志雄・日野葦平・川端康成・尾崎一雄・榊山潤・坂口安吾・倉田百三・高倉テル・石川達三など
学問畑では大内兵衛・久留間鮫造・東畑精一・有沢広巳・中山伊知郎・室伏高信・松本慎一・速水啓二・服部之聡・井口昌雄・古在由重・松村一人など
ジャーナリストでは緒方竹虎・実土路昌一・伊集院兼雄・実堀埓・三谷水平・日色恵・青木新平・倉島竹二郎など
その他書道の柳田泰雲・内山雨海、画家の橋浦泰雄、松竹の田岡啓一、出版界の山崎剛平・河出孝雄・下中弥三郎・鈴木三重吉などなど、百名を越えていたといいます。(1977年現在)
いつも『もの言う翔年』を読んでくださりありがとうございます。お陰さまで「囲碁」も「政治評論」のジャンルもランキング上位に入っております。コメントをいただいたり、ランキングがそこそこにとどまっているのを励みにBlogを書いております。お暇なときに見てくだされば嬉しいです。にほんブログ村にほんブログ村
- 運営会社
- 利用規約
- プライバシーポリシー
- 特定商取引表示
- ご利用上の注意(関連法規)
- 広告掲載・取扱商品
- ヘルプ/お問い合わせ
- サイトマップ
- ご注意【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、東京商品取引所、堂島取引所、 S&P Global、S&P Dow Jones Indices、Hang Seng Indexes、bitFlyer 、NTTデータエービック、ICE Data Services等から情報の提供を受けています。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 『みんかぶ』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者、情報提供者及び広告主は一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「証券取引等監視委員会への情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。 また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
2013/11/13 - ユリウスさんの株式ブログ。タイトル:「碁(ゴ)と棊(キ)の謎 -「古代囲碁の世界」より- 」 本文:

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます
※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
\ 30日間無料で体験しよう /
みんかぶプレミアム会員になる すでに会員の方はログイン