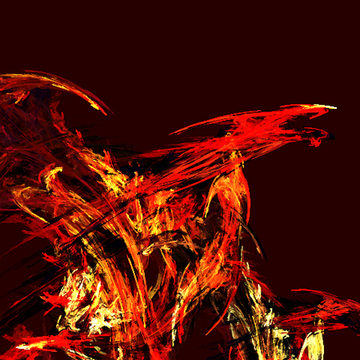…問題有り過ぎだろ。この車。
http://eco.nikkeibp.co.jp/article/column/20110214/105863/
”2月3日に神奈川県の大磯プリンスホテルで開催されたJAIA(自動車輸入組合)主催の合同試乗会に参加した。年に1度開催されるJAIAの試乗会には毎回、100台を超える輸入車が勢揃いする。今年も、GM(ゼネラル・モーターズ)、フォード、クライスラーのアメリカ勢、PSA(プジョー・シトロエン)、ルノー、ダイムラー、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ、BMW、ジャガー、フィアット、ランボルギーニ、ボルボなどの欧州勢が最新のクルマを持ち込んできた。
韓国の小型EV「eZONE」
私はジャーナリスト仲間と一緒に、フィアット「500アバルト」やシトロエンの「C3」、「DS3」などの小型車から、ポルシェの「911カレラ」「パナメーラ」「ボクスター」という3台のプレミアムカー、電気モーターだけでも走れるフルハイブリッドシステムを持つBMWの「アクティブハイブリッド X6」など、全部で9台のクルマに試乗した。ちょっ変わったところでは、韓国CT&T社のコミューターEV「eZONE」(2人乗りの小型電気自動車)にも、試乗会が終わる間際に乗ることができた。
1日で値段も性能も動力源も異なる様々なクルマに乗っていると、何に乗っているのかわからなくなってくるときもあるのだが、それでもポルシェやハイブリッド車、EVとそれぞれ際立った特徴を持ったクルマに触れると、いろいろ思いを巡らせてしまう。
例えば、ポルシェはやはりドイツのアウトバーンを200km/hで走らないと本当の良さはわからないんだろうなと感じたり、欧州の小型車は日本の道にもけっこう合っているななどと感じては、燃費も非常によくなってきているので、日本車の燃費神話はいつまで続くのだろうか、などなど・・・。
そんな1日の最後に乗ったeZONEは、これもまた、いろいろ考えさせられることの多いクルマだった。
近距離移動がコンセプトのeZONEは、そもそも、それほどの動力性能を持っているわけではない。モーターの出力は7kW(約9.3馬力)で、軽自動車の4分の1程度しかない。けれどもEVは一般的に、定格出力の割に低速域からトルクが大きいのが特徴だ。カタログにトルクのスペックが出ていなかったので、自分の身体で確かめるつもりで試乗した。
国道1号線で電欠
乗り込んでまず、メインスイッチをオンにし、前進/後退/ニュートラルの切り替えスイッチを「前進(D)」にする。このスイッチなど、ありふれた家庭の照明用をそのまま借用してきたような感じで、全体に手作り感があふれていた。ゆっくりアクセルを踏み込んでいくと、「フニョニョニョニョ~」という頼りないモーター音とともに、ソロソロと動き出した。
あまりトルクを感じないなと思い、アクセルを思い切り踏み込んでみたが、ダッシュ力に大きな違いはなかった。航続距離を伸ばすために低速域でのトルクを意図的に抑えているのかもしれないが、EVならではの味の1つが薄くなってしまった印象があった。街乗り中心のクルマではあるし、電池に負担をかけたくないのもわかるが、もう少し力強さがないと、「EVはノロい」という誤ったイメージを持たれてしまうような気がした。
徐々にスピードを上げていくと、ちょっとフラフラする感触があり、路上のわずかな段差や轍(わだち)などにも敏感すぎてクルマの姿勢が定まりにくい。まあ、走りの調整の悪さは欧米のコミューターEVにもあることなので、大目に見られないこともない。
ついでに言えば、カタログによれば一定の衝突安全試験をクリアしたということなので、見た目や触った感じから受けるペコペコ感とは違う頑丈さも持っているのかもしれない。問題なのは、その後だった。
試乗の順番が最後だったこともあり、乗る前から電池残量が少ないのは承知していた。それほど距離を走るつもりはなかったが、電欠の時にどんな動きをするのか知っておきたいという少々ひねくれた期待感もあったので、不安があったわけではなかった。
そんなことを考えながら、夕方の国道1号線を大磯プリンスホテルに戻る途中、あと2kmくらいのところで電池が切れた。急に、ストン!という感じで前に進む力がなくなった。
電欠は、長くEVに乗っていれば経験することだ。それ自体はガス欠と同じなので慌てることはない。このときも、路肩に寄せて止めようと思い、おもむろにハザードのスイッチを押した。
ところが、ハザードがつかない。おや?と思ってウインカーを出そうとしたが、やはり何も出ない。もしかして…と思い、メーターパネルに目を向けると、LEDランプなども消え、真っ暗になっていた。ここまできて「これはマズイ」と、少し焦った。夕方になって少し交通量が増えてきた国道で、後続車に合図する手段が何もないのだ。
動かない安全装置
EVはメイン電池の残量がわずかになると、完全放電などによる電池への負荷を避けるために保護回路が働き、メイン電源を落とすなどの制御をすることがある。しかしその場合でも、ライトやウインカー、ハザードなど補機と呼ばれるシステムは、12Vの補機用電池で動くようにしておくのが普通だ。緊急時の安全確保のためである。これはガソリン車でも同様で、いわば最後の保険のようなものだ。
ところがeZONEは、補機用電池がないのか、メイン電池の保護回路が働くと同時に、すべてのシステムがシャットダウンしてしまった。ウインカーも働かず、パワーウインドウなので窓も開けられない。緊急時の“保険”がないのはがいかに怖いか、改めて思い知った。後続のクルマにしてみれば、こちらが単にノロノロ運転を始めたくらいにしか見えないわけだから、しばらくは抜くに抜けず、ちょっとした混乱を招いてしまった。eZONEのこのシステムは、安全面で問題があると言わざるを得ない。
そんなeZONEだが、鉛電池仕様で163万円、リチウムイオン電池仕様で225万円以上の値札が付いている。ちなみにポルシェのスポーツカー「ボクスター」は600万円強だ。つまり、eZONEが“2台半”で、ポルシェが買えることになる。両者を比較するのはジャンル違いも甚だしいが、それにしてもモヤモヤしたものが残ってしまう。
実はこのモヤモヤ感は、ときおり新聞やテレビで見かけることのある、改造EVビジネスにもつながるモヤモヤであった。新しいことに挑戦するのは大事だが、冷静に考えると、コトはそれほど簡単ではないと思えてしまうのだ。
もちろん、EVは発展途上にあるから、価格が高めになるのはいたしかたない。これは大手メーカーが作ろうが、中古車を改造してEVにしようが、同じことだ。主要部品であるモーターやコントローラー、電池などがそれぞれ高いのだからどうしようもない。
それでも自動車メーカー製EVは、量産効果が出れば間違いなく価格は下がる。現時点でも、量産エンジン車との共通部品が多いので、EVだけを作るよりは安く製造できていると言える。
スモールビジネスの試練
しかし、中古車を改造したEVは事情が違う。改造EVでは量産ラインを作るのはムリだし、そもそも中古車を改造するのであれば車体代のほかに、モーターやコントローラー、電池などのパーツ代、取り付け部材の加工費、それに人件費などが上乗せされる。モーターや電池などは、しばらくしたら価格は下がるだろうが、それでも購買力のある自動車メーカーと仕入れ価格を競うなど無理な相談だ。
しかもそうしてできあがったEVは、補機類が全滅するようなシステムは論外としても、走行性能や乗り心地などはeZONEに代表されるような作りになることが多い。少なくとも、今まではそうだった。前述したような理由から、そこそこの性能の小型車でも、一般的な装備を備えようとすると、部品代だけで何百万円にもなってしまうからだ。
価格を下げるためには、サスペンションの性能を落としたり、内装を安くしたり、装備を減らしたりしながら、原価を物理的に削るほかない。
もちろん好き嫌いは人それぞれなので、高価で性能がそこそこのクルマが売れないとは言い切れない。古いクルマを手放しがたくて改造する人も少なくないだろうし、モノを大事にするのは環境にもいい。しかし、そうしたクルマが日本で毎年数万台、数十万台売れるようになるとは、私にはちょっと想像しにくい。数が出なければコストも下がらない。こうした事情を考えると、改造EVの価格が市場で競争力を持つほどに下がるとは、どうも考えにくいのである。
改造EVではないが、例えばユニークな小型車などの製造で知られるタケオカ自動車工芸(富山県富山市)のように、一定の顧客をつかめれば事業を続けられる可能性はある。ただ、そのためにはキメ細かなユーザーニーズの掘り起こしとユーザー対応が必要だ。これは一朝一夕にできるものではない。
1990年代、アメリカでは改造EVを手掛けるベンチャーがいくつも立ち上がった。それと同じように、日本でも改造EVをビジネスにする企業は増えるかもしれない。しかし前途は多難だ。アメリカでも当時のベンチャーのほとんどは、すでに表舞台から去った。
重要なのは、改造EVであれCT&Tのようなベンチャーであれ、EVを作ったり売ったりする企業がなくなってもクルマは残るということだ。だからこそ市場で販売されるEVには、どんなにコストを削ろうとも最低限の安全装置くらいは着けておいてほしいのである。この点、EVの動向を伝えるメディアの責任はいわずもがなだが、ユーザー側でも注意して見ていく必要があるように感じている。”
安全装置がマトモじゃない車なんて危険で乗れませんよ。
(緊急時のハザードがつかないとか車として有り得ませんから)
少なくとも現在、走っている車程度の安全性が無いとね。
…しかし、良く日本で走る許可が出たな。この車。