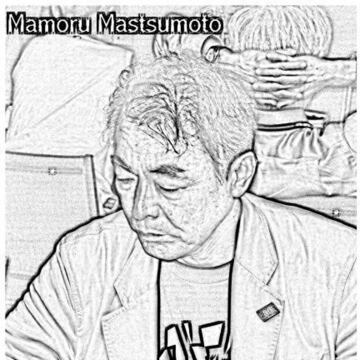10月25日のエントリー「財政規律を守れ! -民主党に望む」で既に書いたことなのだが、このことは何回言ってもいいすぎではない。翔年が言っているのではなく、国債通貨基金(IMF)がハッキリ指摘してくれているのだから。
新しい数字で再確認しておきたい。
国債通貨基金(IMF)が11月3日に、世界20カ国・地域(G20)の債務残高見通しを公表した。わが国については「財政出動圧力が特に強い」と指摘し、2014年には国内総生産(GDP)の約2.5倍に拡大すると全世界に向かって公言している。そのうえ、さらに経済危機対応政策を平時に戻す「出口戦略」を「すぐに策定すべきだ」と警告している。下の数字を見て、わが国の財政が如何にひどいことになっているか、誰の責任でこうなったのか、これをどのように立て直すのか、政治家はキチンと国民に説明をすべきだと思う。(長年にわたる自民党政権がこのような事態に至らしめたもの。民主党はわが国のこの危機をどう救おうとするのか? その道筋を示せ!)
G20主要国の政府債務残高(IMFによる、GDP比)
2009年 2014年
日本 218.6(%) 245.6(%)
米国 84.8 108.6
英国 68.7 98.3
ドイツ 78.7 89.3
中国 20.2 20.0
インド 84.7 78.6
ブラジル 68.5 58.8
ロシア 7.2 7.2
G20平均 38.9 36.2
翔年は思う。わが国の政治家は国民に甘いことばかりささやいて、金をばらまく政府ばかり作る。自民党もひどかったけれど、最近の民主党を見ていると、もっとひどいことになるかも知れないと危惧する。小泉元総理は国民に痛みを伴うことを「改革なくして成長なし」と大声で叫んだが、鳩山総理にはそういうリーダーシップはとれないらしい。国民が痛みを感じる政策は一つもとらず、「国民目線」(嫌いな言葉だ)とか言って、国民におもねった政策ばかりだと、わが国の将来に大きな禍根をのこすことは間違いない。リーダーには大所高所に立った判断と決断が不可欠だと信じる。
国の財政破綻は具体的にどのような事態になるのだろうか? 多分、ハイパーインフレが起るのだろう。(別の見方があったら、教えてほしい)
1 わが国は敗戦直後の昭和21年に経験している。国債(戦時国債)は紙切れ同然になった。その後のインフレはすざましかった。
これは戦争のせいというなら、ロシアを見よう。
2 ロシアでは1998年、国内大手銀行の多くが営業停止となり、人々の預金は封鎖され、物価は高騰し、国家財政は破綻した。この時はルーブル通貨は3分の一の価値(物価は3倍)になり、国民の財産は三分の一になった。その後も通貨は下がり続けて4年後には物価は1800倍になった。
なぜ、こうなったのか? ロシアの国家財政は、「国債発行で作った借金を国債を発行して返済する!」という、自転車操業状態だったからである。わが国の現状はそれによく似てきた。
政権党はこれ以上のバラマキ政策はとってはならないと思う。識者はこのことをもっと政治家や国民に説くべき義務があると思う。
かつてわが国が戦争に突っ走しろうとした時、頭で無謀なことと理解していた識者がいたはずなのに、だれも身を呈してこれを止めようとしなかった。いたかも知れないが少数派の声はきわめて小さかった。新聞も世論も戦争に向かって突き進むことしか頭になかった時代に、それをあげつらうのは酷という意見があるが、翔年はそうは思わない。識者といわれるインテリは、その時、言論の武器で戦う義務があったのだ。戦後になってから、「あの戦争が勝てないと私は知っていた」と言い出した恥ずべきインテリは大勢いたけれど、これでは識者の値打ちはない。大衆と同じ。
いま、財政について識者はきちんとした論理を持って、政治家や世論に働きかけるべき最終の時期ではないかと思う。
行政刷新会議で「仕分け作業」でムダを洗い出すのはいい。ただし、財政についてのグランドデザインが民主党には欠けている。マニフェストには書いてない。
いくらムダを排除しても、それらが代わりの歳出に回されるようでは、借金漬けはいつまで経っても終わらない。
奈落の底へ向かって一直線に進んでいるように見えるが、これは杞憂なのか?
- 運営会社
- 利用規約
- プライバシーポリシー
- 特定商取引表示
- ご利用上の注意(関連法規)
- 広告掲載・取扱商品
- ヘルプ/お問い合わせ
- サイトマップ
- ご注意【ご注意】『みんかぶ』における「買い」「売り」の情報はあくまでも投稿者の個人的見解によるものであり、情報の真偽、株式の評価に関する正確性・信頼性等については一切保証されておりません。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc.、東京商品取引所、堂島取引所、 S&P Global、S&P Dow Jones Indices、Hang Seng Indexes、bitFlyer 、NTTデータエービック、ICE Data Services等から情報の提供を受けています。 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。 『みんかぶ』に掲載されている情報は、投資判断の参考として投資一般に関する情報提供を目的とするものであり、投資の勧誘を目的とするものではありません。 これらの情報には将来的な業績や出来事に関する予想が含まれていることがありますが、それらの記述はあくまで予想であり、その内容の正確性、信頼性等を保証するものではありません。 これらの情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社、投稿者、情報提供者及び広告主は一切の責任を負いません。 投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「証券取引等監視委員会への情報提供」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。 また、『みんかぶ』において公開されている情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を転用、複製、販売、加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。
2009/11/12 - ユリウスさんの株式ブログ。タイトル:「わが国の財政は奈落の底に落ちる -G20の政府債務残高」 本文: 10月25日のエントリー「財政規律を守れ!

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます
※サイトからのお知らせは除きます
※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
\ 30日間無料で体験しよう /
みんかぶプレミアム会員になる すでに会員の方はログイン